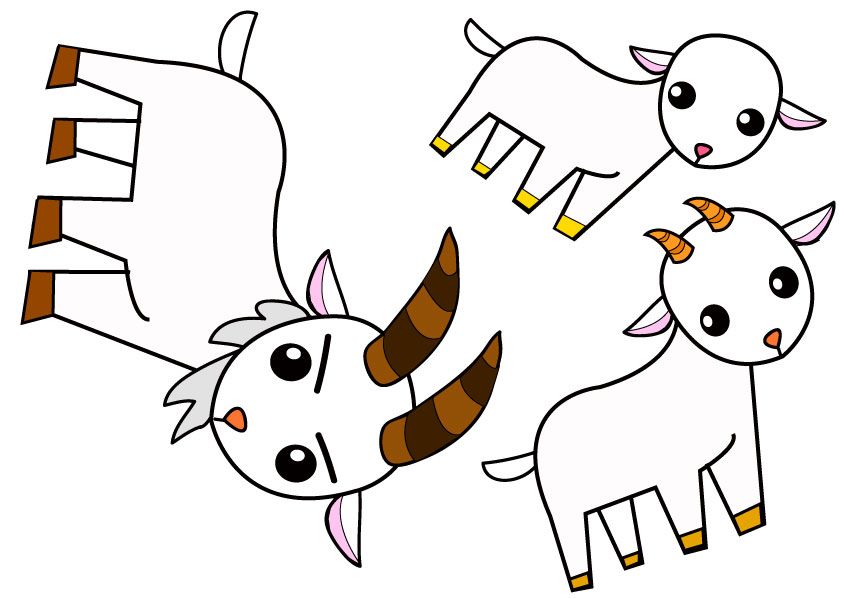
こんにちは、のんしんです。
この記事では、「保育士試験を独学で合格した方法-実技試験編(言語)」をテーマに書いています。
保育士という資格について、昨今人材不足から需要が高まってきています。この資格を取得しようと考えている方も少なくありません。
私も令和6年度後期保育士試験を受け、一発合格することができました。対策方法としては、通信講座や講習などは受けず独学で合格しています。
保育士を取りたいけれども費用を抑えたいと思われる方もいると思います。また独学は対策時間のスケジュールも組みやすいというメリットもあります。その反面自分で対策方法を確立させていく必要性があるので、不安も生じやすくなります。
今回は保育士試験を独学で合格したいと考えている方に向け、私がどのような対策をして保育士試験を一発合格したかをお伝えします。ぜひ最後までお読みいただけると嬉しいです。
また保育士試験は筆記試験と実技試験があります。今回は実技試験(言語)についてお伝えします。
※令和7年度より保育士実技試験言語の内容に変更があります。そのためこの記事では私の経験した令和6年度保育士実技試験(言語)の内容を元に対策方法をお伝えしていますのでご了承ください。変更点は記事内にまとめています。
筆記試験及び実技試験(造形)に関しては別記事「保育士試験を独学で合格した方法-実技試験編(造形)」及び「保育士試験を独学で一発合格した方法-筆記試験編」を参考にしていただけますようお願いします。
※実技試験では音楽も選択できますが、私は音楽の試験を経験していません。その為情報をお伝えすることは困難であると思い、記事にはしていませんのでご了承ください。
保育士実技試験言語の変更内容
保育士実技試験言語の令和7年度変更内容について説明します。
この試験では、「子どもたちにお話しする技術」が求められます。3分間の素話でお話をまとめます(道具などを使用できません)。想定は3歳児クラス15人程度に素話をします。お話内容は事前に決められています。
令和6年度はお話内容が全部で4つありました(ももたろう、3びきのこぶた、おおきなかぶ、3びきのやぎのがらがらどん)。その中から自分で自由に選択し、試験で素話を行いました。
しかし令和7年度はお話内容が3つになりました(ももたろう、3びきのこぶた、おおきなかぶ)。その中から試験で試験官から1つお話内容の指定があり、素話を行います。
つまりお話内容が1つ減り、自由に選択できなくなったのです。
個人的には変更により難易度が上がったと感じています。なぜなら1つのお話内容を対策すればいいのではなく、3つ全て対策しなければなりません。そのため令和7年度からは実技試験言語の対策時間は増えるのではないかと捉えています。
詳細は一般社団法人全国保育士養成協議会のホームページにてご確認ください☟
言語対策時間は「18時間」を目安
実技試験言語を受ける方は、対策にどのくらい時間を要するか気になるところだと思います。私の経験から言語対策時間は 「20時間」を目安にするといいと思います。
お話一つの対策時間が6時間です。それが3つで18時間となります。私の場合1日3回3分間を意識して全ての素話を練習しました。朝・昼・夕で1回ずつ練習し、身振り手振りを行う練習及び時間を測った練習は、昼に行っていました(仕事での休憩時間中に行いました)。
また素話は台本を用意すると練習しやすいです。私はテキストを参考にし、自分の読みやすいようにアレンジした台本を作りました。この台本を1つ作るのに40分ほど時間が必要す。台本には①題名②お話内容③おしまい、ありがとうございましたのあいさつまで入れておきます。
素話の練習と台本を作成する時間を合わせて対策時間が20時間となります。
また令和7年度は実技試験(言語)のお話内容ではなくなりましたが、令和6年度のお話内容の一つである「三びきのやぎのがらがらどん」の実際使用した台本を紹介しています。よろしければ別記事「保育士実技試験言語用の台本(三びきのやぎのがらがらどん)」を参考にしてみてください。
必要なものについて
私は実技試験(言語)対策では①テキスト②台本を使いました。
各使用方法は以下の通りです。また実際に使用したもののリンク先も貼ってありますので、参考にしてください。
1.テキスト
テキストは始めに読みました。お話内容のまとめ方や、例が記載されていました。お話の例をそのまま使用して良いのですが、読みやすいように台本を作りかえても良いかと思います。こちらが私の使用したテキストです☟
※ただしテキストは毎年変更がありますので、最新のものをご用意してください。
2.台本
テキストをもとに台本をつくりました。とにかく台本は読み込みます。ストップウォッチで時間を測り、2分45秒~3分でまとまるとベストだと思います。それより短いもしくは長い場合、台本を見直し、話の速度が適切かを確認します。
素話を他の人に見てもらう
必須ではありませんがわたしは重要である捉えています。素話は前述した通り、3歳児クラス15人程度を想定し行います(実際に15人の子どもがいるわけではありません)。つまり一点だけ向いて素話をする、3歳児に聞き取りづらい話し方などではいけません。子ども相手に話す機会があればいいのですが、他の人に聞いてもらうことでも自分がどのように話しているかわかります。もし難しければ、スマホで録画し、自分の素話の姿を撮り確認すると良いかと思います。
実技試験(言語)の流れ
令和6年度実技試験(言語)の経験をもとに、試験の流れを説明します。まず自分の順番が来たら、試験が行われる部屋に入ります。部屋に入ると試験官が座っています。私の場合は女性の試験官が2人座っていました。
後は試験官の指示に従って試験を進めます。大まかにですが、
①あいさつをしお辞儀をする(失礼します、よろしくお願いしますなど)
②荷物を指定の場所に置く
③椅子が置いてあり、椅子の前に立つもしくは座る
④試験官の合図で開始(私の場合、準備ができたら始めるように伝えられました)
⑤試験が終了し荷物を持ちあいさつ(ありがとうございました、失礼しました)
⑥退室
の流れでした。多少違いはあると思いますが、この流れは知っておくと良いかと思います。
余談ですか私は言語の試験が行われる部屋を間違え、遅刻してしまうという事がありました。別記事「保育士試験で遅刻した結果どうなったのか?」にて紹介していますで、もしよろしければ参考にしてみてください。試験会場の確認には十分に注意しておきましょう。
ここまで記事をお読みいただきありがとうございます。ここまでの内容は前述した通り、私の経験からお伝えしたものとなります。試験ごとに内容の変更もあるため、あくまで経験から予測した記事になります。
ただ実際に私はこの方法で保育士実技試験言語を一発合格しています(結果は35点で、50点中30点以上で合格となります)。合格した人の対策方法を参考にすることも良いかと思います。
これから保育士を目指す方に少しでもお役に立てれば嬉しいです。



コメント